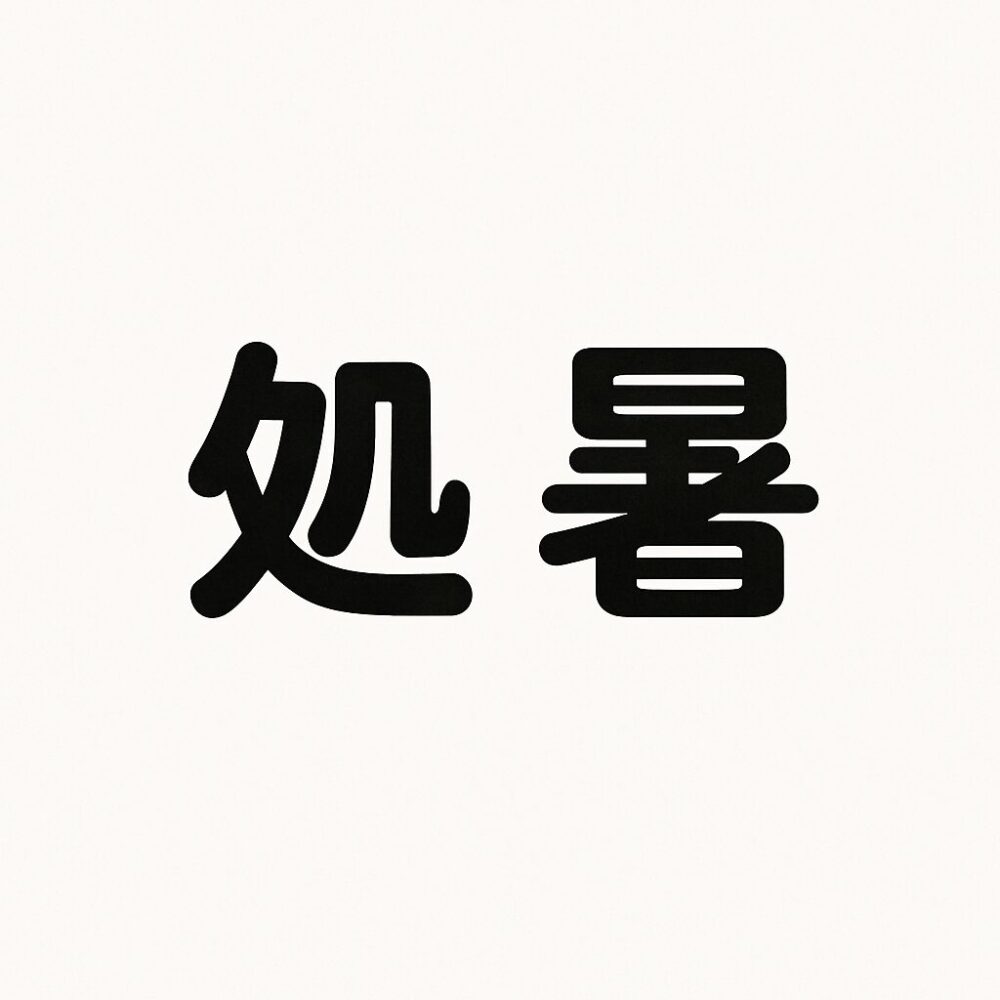「処暑(しょしょ)」という言葉を聞いたことはありますか?
8月23日ごろに訪れる二十四節気のひとつで、「暑さが和らぐ頃」とされるタイミングです。
とはいえ、現代ではまだ蒸し暑い日が続いていたり、天気が不安定だったり…。
本当に季節が変わり始めているのか、ピンと来ない方も多いかもしれません。
でも実は、この「処暑」の前後には、気温・空気・体調などにちいさな変化のサインが現れやすい時期なんです。
今回はそんな「処暑」の意味と、現代の暮らしに取り入れたい5つのヒントをご紹介します。
朝晩の“気配の変化”に目を向けてみる
処暑の頃、日中の暑さに変わりはなくても、朝や夜にふと風の涼しさを感じる瞬間が増えてきます。
「虫の音が変わった」「空が澄んで見える」――そんな小さな変化は、季節のスイッチを教えてくれるサイン。
これらの変化に気づくだけで、毎日の生活に少し“余白”が生まれ、気持ちにもゆとりが出てきます。
何気ない日常の中にある「季節のきざし」に意識を向けてみると、暮らしのリズムも整いやすくなります。
食べ物から季節を感じる|“土用明け”の食の見直し
処暑の頃は、ちょうど「土用(夏の終わりの時期)」が明ける頃でもあります。
この時期は、冷たい飲み物や刺激物の摂りすぎによる“夏疲れ”が出やすい時期。
そんなときは、冷たいものを控えて、温かい汁物・やさしい味の煮物・発酵食品などを取り入れるのがおすすめです。
胃腸をいたわることで、残暑を乗り切る体の土台が整います。
季節の変わり目には「食の切り替え」も大事なケアのひとつです。
服装や室温調整で“冷え疲れ”を防ぐ
処暑を過ぎても、室内はエアコンが効きすぎていたり、汗をかいたまま過ごすことが多くなりがち。
こうした状態が続くと、じわじわと“冷え”が蓄積して、だるさや肩こり、寝つきの悪さにもつながります。
そんなときは、薄手の羽織りや腹巻、レッグウォーマーなどで“ちょっとした冷え対策”を。
寝るときにタオルケットを1枚足すだけでも体調が整いやすくなります。
処暑は「秋の冷え」の入り口。早めに意識しておくことで、体の疲れが残りにくくなります。
小さな“季節の入れ替え”を始めるチャンス
まだ真夏の感覚が残る8月下旬ですが、処暑をきっかけに少しずつ秋の準備を始めるのもおすすめです。
たとえば、
ルームウェアを少し落ち着いた色味に変える
寝具にガーゼ素材を加える
ハンカチや靴下を秋物に入れ替える
…といった、「肌に触れるもの」からの入れ替えなら、気軽に気分も切り替わります。
全部を一気に変えなくてもOK。
1つずつ、“季節を意識する習慣”を取り入れていきましょう。
季節のサインを“暮らしのリズム”に取り入れる
処暑は、ただ「暑さが落ち着いてくる」というだけではなく、心や体にとっても“ゆるやかな変化”のスタートラインです。
朝晩の風の変化に気づく
食事で内側から整える
冷え対策で疲れをためない
少しずつ持ち物を秋仕様に変える
そんな小さな工夫が、疲れにくい暮らしのリズムをつくってくれます。
「もう夏も終わりかぁ」と流すのではなく、“次の季節への橋渡し”として処暑を楽しむ――
そんな感覚を持てると、日々の生活にちょっとした心地よさが増えていきます。