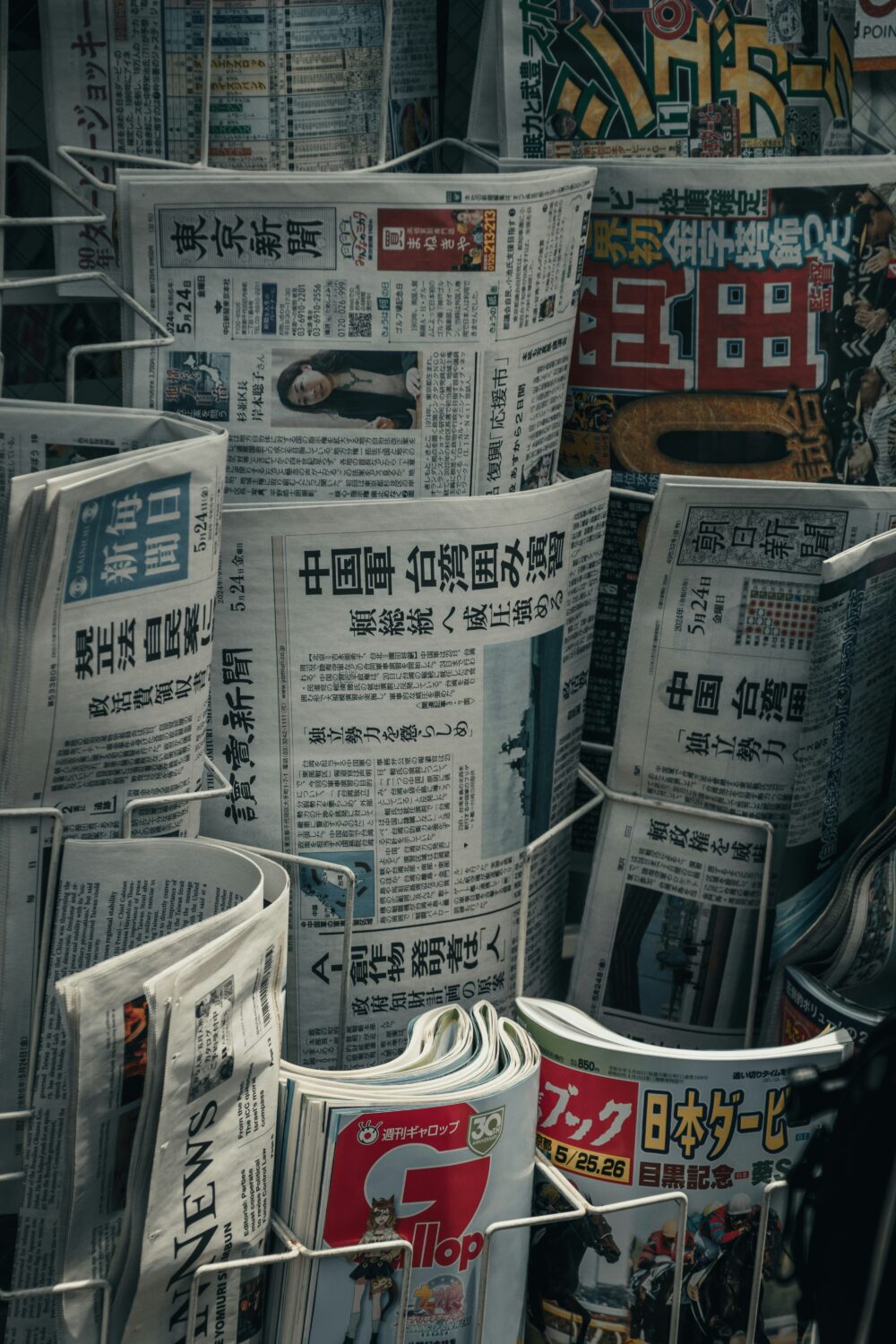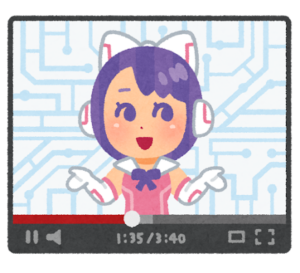SNSやネットを開くと、毎日のように目に飛び込んでくる「衝撃的なニュース」。
「芸能人の不祥事」「大規模災害の速報」「医療や健康に関する注意喚起」など、つい信じてシェアしたくなる情報も多いですよね。
ところが、よく調べてみると実際は根拠がなかったり、誰かが作ったフェイクニュースだったりすることも少なくありません。
特に若い世代はSNSから情報を得る割合が高く、拡散スピードも速いの「だまされやすいリスク」と常に隣り合わせです。
では、だまされにくい人はどんな工夫をしているのでしょうか?
今回は、知識や専門性がなくてもすぐに実践できる「シンプルな習慣」を5つご紹介します。
ニュースアプリを2つ以上使う
だまされない人の特徴のひとつは、「ひとつの情報源だけに頼らない」ことです。
たとえば、Twitter(X)のトレンドで見かけたニュースをそのまま信じるのではなく、Yahoo!ニュースやNHKニュースなど、信頼性のあるニュースアプリで裏を取る習慣を持っています。
同じニュースでも媒体によって表現や見出しが違い、印象が変わることがあります。
複数の情報源を比較することで、偏った情報に振り回されにくくなるのです。
感情をあおる記事は一度立ち止まる
「えっ!本当に!?」と驚く記事ほど注意が必要です。
特に「怒り」「不安」「恐怖」など強い感情を刺激する情報は、事実よりも「拡散力」を優先して作られている場合が多いです。
だまされない人は、そうした記事を見てもすぐにシェアせず、「本当に信じていいのか?」と一呼吸置くことを習慣にしています。
心を落ち着けるだけで、冷静な判断がしやすくなります。
発信元を確認するクセをつける
フェイクニュースの多くは、発信源が不明確です。
例えば「○○の専門家が警告している」という書き方をされていても、実際に調べてみるとその専門家は存在しない…というケースも少なくありません。
信頼できるニュースは必ず「どこが発表したのか」が明確です。
新聞社、テレビ局、政府機関、大学研究室など、公的な機関の名前があるかどうかを確認するだけで、誤情報を避けやすくなります。
時間をおいてから確認する
速報性が高いニュースほど、不確かな情報が混じりやすいものです。
だまされない人は、衝撃的な記事を見ても「今すぐ拡散しない」ことを徹底しています。
数時間から半日待つだけで、メディアや公的機関が事実確認をして続報を出すケースが多いため、正確な情報に近づけるのです。
「後から訂正記事が出て恥ずかしい思いをする」より、「少し待って確実な情報を得る」ほうが結果的に賢明です
「調べてから話す・シェアする」を習慣にする
だまされない人は、情報を受け取った時点で「調べる」ことを欠かしません。
たとえば、画像や動画なら逆画像検索をして出どころを確認したり、Googleでニュースタイトルを検索して複数の記事を比較したり。
わずか数分の確認で「誤情報を広めるリスク」を大きく減らせます。友達や家族に話す前に、シェアする前に「ちょっと調べてみる」ことを習慣化するのが効果的です。
フェイクニュースにだまされない人は、特別なスキルや知識を持っているわけではありません。
彼らがやっているのは、次のような小さな習慣です。
情報源を2つ以上確認する
感情をあおる記事は一呼吸置く
発信元を必ずチェックする
拡散は急がず時間をおく
調べてからシェアする
SNSやネットは便利ですが、同時に誤情報があふれる場所でもあります。
今日からできるちょっとした工夫で、「だまされにくい自分」をつくっていきましょう。