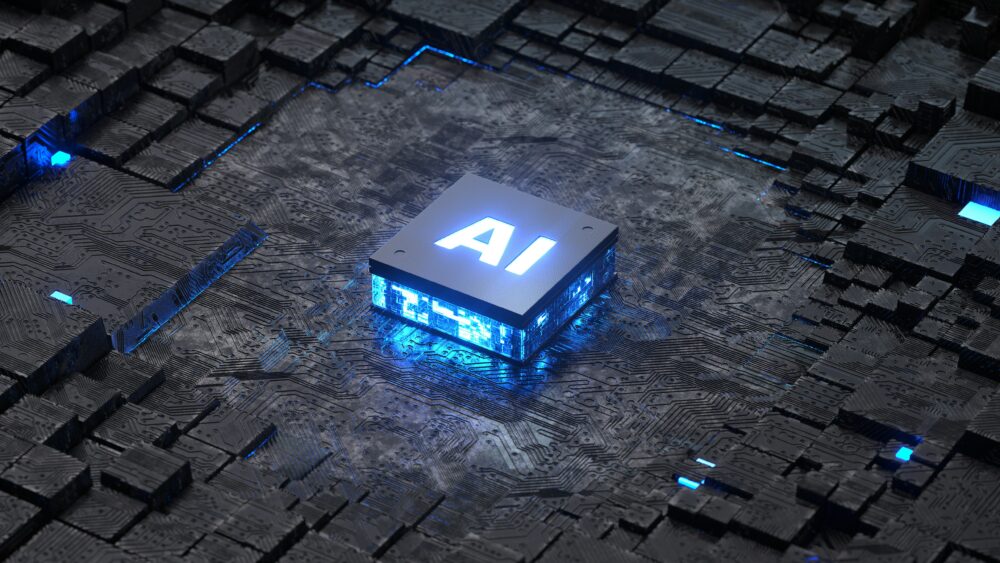「大学に行けば就職は安泰」――そんな常識がアメリカで音を立てて崩れています。
AI(人工知能)の普及によって、かつて若者がキャリアの第一歩として踏み出していたエントリーレベルの仕事が次々と消えているのです。
求人は減少し、応募者は増加。結果として、学位を手にしても就職先が見つからないという深刻な事態が広がっています。
今や「大卒=安定」という神話は過去のものとなりつつあるのです。
AIの波が「大卒」すら飲み込む
アメリカの求人プラットフォームの調査によれば、エントリーレベルの求人は前年比で15%も減少しました。
一方で、応募者は30%増加しており、競争は熾烈さを増しています。
AIが事務処理や基礎的なプログラミング業務を肩代わりすることで、そもそも人を採用する必要がなくなってきているのです。
その影響は一流大学の卒業生にまで及んでいます。
かつて高収入が約束されていたコンピュータサイエンスの専攻者ですら、職に就けずに飲食店で働くケースが急増。
学位があっても、AIに代替される仕事を選んだ瞬間に道が閉ざされてしまう現実が突きつけられています。
就職市場の“再構造化”
Wall Street Journalの報告では、2024年に大学新卒者の採用数は全体のわずか7%にまで減少したとされています。
かつて企業にとって不可欠だった「新卒の底支え」も、AIと自動化に置き換えられつつあるのです。
さらにJPMorganの分析では、「jobless recovery(雇用なき回復)」という言葉が使われています。
経済は回復しても雇用は戻らない。
とりわけホワイトカラー職の新規採用は構造的に縮小し、若者にとって「就職の椅子取りゲーム」はますます過酷になっているのです。
学位の価値が揺らぐ時代
「学位さえあれば安泰」という考え方も崩れつつあります。
調査では、Z世代の約半数が「AIの普及によって大学の価値が下がった」と感じていることがわかりました。
特に象徴的なのは、これまで安定職の代名詞だったコンピュータサイエンス専攻です。
AIがコードを書き、バグを修正する時代において、初級プログラマーの仕事は真っ先に切り捨てられています。
教育への投資がリスクと感じられる一方で、企業は「実践力」や「創造性」といった、学位では測れない力を求める傾向を強めています。
つまり、大学名よりも「何ができるのか」を証明できる人材だけが生き残れるのです。
生き残るための戦略
では、どうすればこのシビアな現実を突破できるのでしょうか。
第一に必要なのは、AIを恐れるのではなく使いこなす力です。
履歴書や自己PRをAIで効率化するだけでなく、仕事そのものをAIと協働しながら進められる人材こそが評価されます。
次に重要なのが、AIが苦手とするスキルを磨くことです。
問題解決力や創造性、対人スキルといった「非定型業務」に強みを持てば、代替されにくい人材となります。
さらに、インターンや小さなプロジェクト経験を積むことで、学位以上に“現場で役立つ力”を示すことが可能です。
まとめ
AIによる雇用の再構造化は、若者のキャリアの入口を根こそぎ変えつつあります。
「大学さえ出れば安心」という常識はすでに崩壊しました。
必要なのは、AIと共存できる力を持ち、自らの強みを言語化し、実践で示すこと。
シビアな現実を直視したうえで行動できる人だけが、次のステージへ進めるのです。
学生だけの問題ではありません。AIによる働き方の再編は、すでに社会人にも押し寄せています